どうも、初期設定だけで最低3日はかけるだださんです。
今回はゲーム設定の中でも、
「わかるようでわからない」そして「今さら聞けない」グラフィック設定シリーズの第一弾。
被写界深度について、わかりやすくお届けします!
決してマニアックすぎず、でも「ほう、そういうことね!」と納得してもらえる内容に仕上げました。
ぼんやりしていた疑問が、きっとハッキリするはずです。
……でも、扱うのは“ぼんやり”することについてなんですけどね。
では、さっそく行ってみましょう!
ゲームにおける被写界深度とは?効果や役割を解説
ゲームの設定画面でよく見かける「被写界深度」という言葉。
そもそもこれは、カメラの世界で使われる「ピントが合う範囲(深度)」を指す用語です。
最近では、スマホのカメラでもおなじみですよね。
ポートレートモードで撮ると背景がきれいにぼけて、被写体が引き立つ――
あの“美しいボケ感”が被写界深度の演出です。
ゲームでも、被写界深度をONにすると手前のキャラクターがより目立ち、背景がぼんやりとした雰囲気になります。
逆にOFFにすると、全体がハッキリくっきり表示されるので、見やすさが変わるんです。
これは好みの問題ですね。
ただし、リアルなカメラとは少し違って、ゲームでは「演出用のエフェクト」という役割が強いかもしれません。
ぼんやりとした背景がシネマティックな雰囲気を出してくれる反面、ONにするとハードの負荷が高くなることも……。
被写界深度はゲームに必要?いらない?
この被写界深度、ゲーム内でONにすべきか――
これはやっぱり
お好みでどうぞ
という一言に尽きます。
先述の通り、ONにすると背景がぼんやりとして奥行き感が増し、
その美しさや臨場感にうっとりできるシーンも多いです。
手前のキャラやオブジェクトがしっかり引き立って、よりゲームの世界に没頭できる魅力があります。
実際に、被写界深度ON/OFFの比較画像を見てみると、
背景のぼけ具合やキャラクターの存在感が大きく変わるのが分かると思います。

※わかりやすいように“それっぽい仮のゲーム映像”をサンプルとして作ってみました♪

ONの状態は、まるで写真や映画のワンシーンのようなシネマティックな演出。
一方でOFFの状態では、全体がくっきり見える分、動きの情報をしっかり把握しやすいです。
しかし、問題が……!
こうした美しさの裏には、“負荷の増加”という落とし穴が潜んでいるのです。
見た目のクオリティと、PCやグラボへの負担――
次はその“負荷問題”について、もう少し詳しく触れていきます!
被写界深度のON/OFFでどれくらい負荷が違う?
被写界深度は、キャラクターを引き立てる美しい演出効果ですが、
実はゲーム機やPCにしっかり負荷がかかる設定でもあります。
とくにグラフィックボード(グラボ)に負担がかかるんですよね。
ただし、ここで注意したいのが――
「じゃあ具体的に何fps下がるの?!」なんていう専門的な数値は、
正直この記事では必要ないかなと思います。
だって、実際にプレイする環境や設定の組み合わせで全然違うし、
数字を並べても「ふーん」で終わりがちですからね。
イメージとしては、PS5や、これから発売されるNintendo Switch 2なんかなら
ある程度は耐えられると思います。
でも、他の設定まで高めにしていたら……
ゲーム機が熱を持って、最悪部屋まで暑くなる現象が起きるんですよね(笑)
PCユーザーなら、推奨以上のグラボを積まないと
ファンが全力で回るわ、熱暴走寸前になるわで、まさに夏は地獄!!
冬なら「暖房いらず!」って笑い話にできるけど、
夏はエアコンが必須になるかもしれません。
(※ちなみに被写界深度だけでは部屋がサウナになるほどではないですけどね)
まとめ|ゲームをもっと楽しむために「被写界深度」と向き合おう!
被写界深度は、リアルタイムでONにするとグラボやPCにそれなりの負荷がかかります。
そのため、普段のプレイ中はPCの性能や快適さと相談しながら、ON/OFFをお好みで決めるのが一番です。
私みたいにこだわりだすとゲーム本編そっちのけでいつまでも設定を調整し始めますからね…。
ただ、もし「こだわりの一枚」を撮りたいなら!
スクショモードがあるゲームで大活躍します。
最近では、撮影後にさらに被写界深度を細かく調整できる機能があるゲームも増えています。
例えば「Horizon」シリーズでは、スクショだけで時間が溶けるほどに楽しめます。
オープンワールドゲーム好きな方は、フィールドを歩き回ってお気に入りの絶景スポットを見つけ、
被写界深度を活かして“とっておきの一枚”をぜひ撮影してみてください!
最後までお読みくださいましてありがとうございました



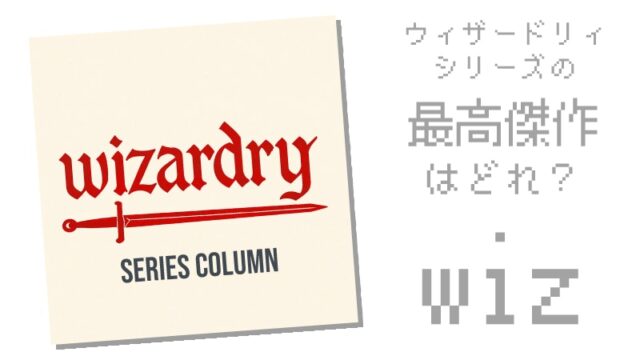
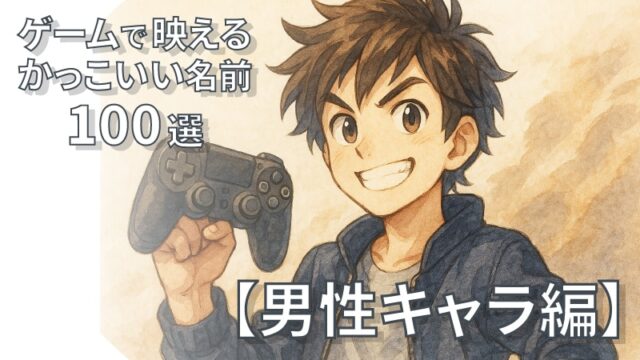
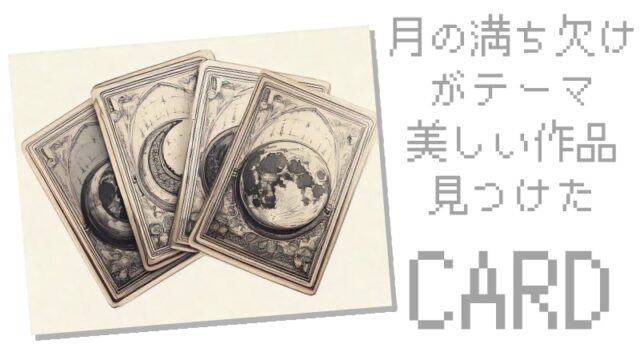

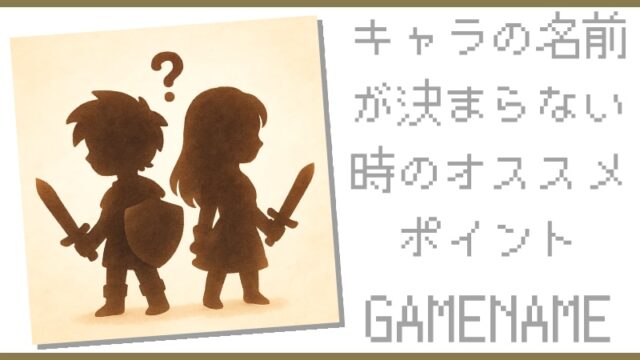







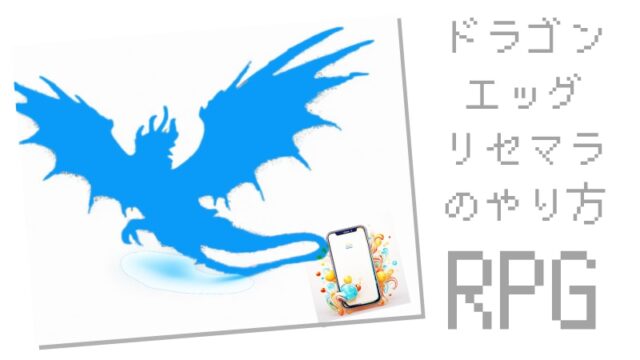
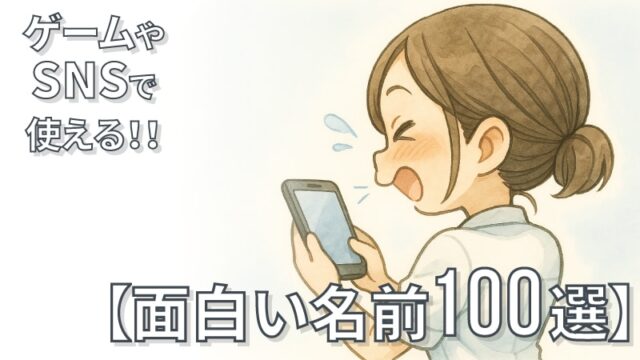
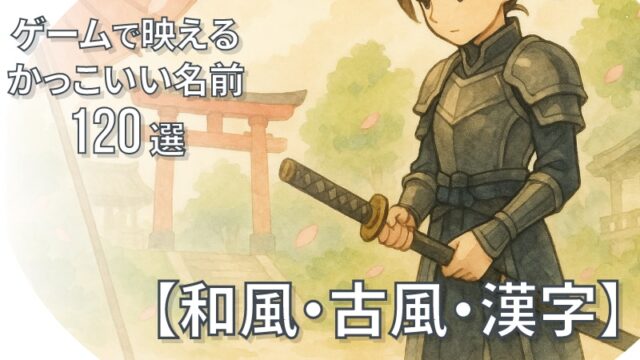

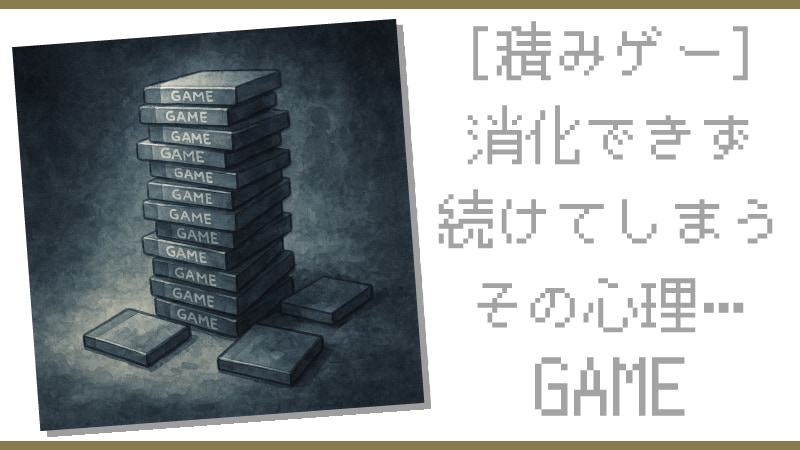
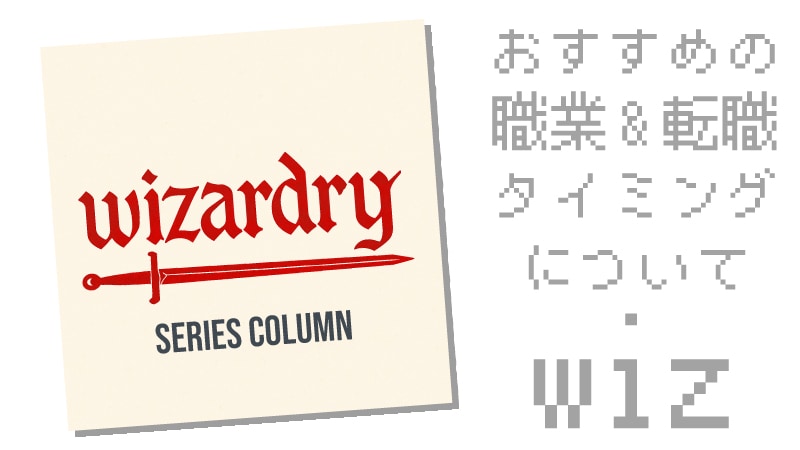

コメント